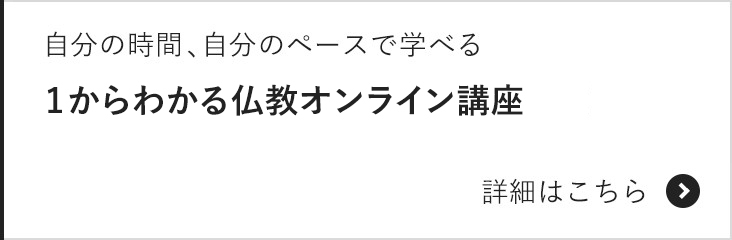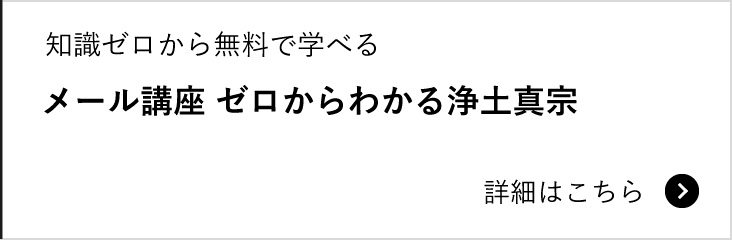360度、どの方角を向いても地平線。吹き抜ける蒼い風に、何億という草が揺れている──。
壮大な大草原にあこがれ、約1年間、モンゴル国立大学に留学した大川恵香さん(仮名)は、
「あの草原にはね、すさまじい〝風〟が吹いているのですよ」
と教えてくれた。
それは大砂塵のようなもの?
「いえいえ、そんなんじゃなくって、人間の作った一切の価値観を吹き飛ばしてしまう、音もしない〝風〟なんです」。
私は思わず身をのり出し、彼女の〝風〟の話に耳を傾けた。
ハラホリンの草原をゆく

それは大川さんがモンゴルに留学した2年前(取材当時)の話である。大学でトゥブシンさんという遊牧民の男性と知り合い、彼の故郷・ハラホリン(カラコルム)の草原を訪ねることになった。10月半ばのことである。

首都ウランバートルの市街地を出てしまえば、あとは果てしない草の海である。でこぼこ道を車でどれだけ走っても、対向車を見かけることはない。
6時間ほど走ったころだろうか、ようやくマッシュルームのような草原の家=包(中国人はパオと読む)が見えてきた。沈みかけた太陽が地平線を赤く染める。この平原をジンギスカン時代を思わせる遊牧民たちが、今も疾駆しているのだ。
モンゴルの歌
その夜、泊めてもらったのは、友人の兄トールガさんの包(パオ)だった。包の外幕は羊毛でできた真っ白なフェルトで、触れてみると分厚く柔らかい。これを簡単な骨組みの上にドーム状にかぶせ、床は草地に絨毯を敷く程度。いかにも移動性住居らしい。そこに家族5人のほか、近所の人々まで集まって大歓迎してくれた。
遊牧民の人たちは、話し方や動作が鷹揚で、年を取ると、100騎や200騎くらい引き連れる精悍な武将顔となる。

ボーブ(揚げ菓子)、ウルム(乳製品の一種)、羊肉が並ぶ。ドンブリで出されたアイラグ(馬乳酒)を飲み干すと、家長からニコニコと「もう一杯」と勧められ、結局3杯も飲んでしまった。
ほの暗い明かりの中、酒を回し飲みしながら順々に客人へ祝福の言葉を述べる。モンゴル人は詩才豊かなのか、どの人の挨拶も詩的で情感があふれる。やがてだれからともなく歌を歌いだした。その哀調を帯びた歌声は心にしみた。
アリガリの煙立ち上る
牧民の家に生まれた私
故郷の草原を
揺りかごだと思う
この人こそモンゴル人
故郷の愛する人よ
生れ落ちたこの大地を
自分の身体のように愛しく思い
産湯にした清らかな川を
母の乳のように懐かしく思う
(作チミド 訳中里豊子)
モンゴルの歌は、草原をたたえたり、父母への感謝を詠ったものが多い。素朴だが、ストレートな詩情は心を打つ。軽い酔いと旅の疲れから、その夜はそのまま眠りについた。
モンゴルでの生活

耳元で鳴く牛の声で目が覚める。天窓からはまぶしいくらいの光の束。
草原に朝が来た。
朝食を済ますと、10歳になる長男のドルジ君が、羊たちを囲いから草地へ連れ出していた。ここでは子供たちも立派な働き手である。自在に馬を操るドルジ君に、馬の乗り方を教わった。勉強するのは移動式の学校が来た時ぐらい。ここでは馬を操る技術のほうが重要らしかった。
 父親のバトさんは、壊れたラジオを直していた。必要になれば狩猟に出る。食事時間は特に決まってはおらず、お腹のすいた時に勝手に食べるようだった。
父親のバトさんは、壊れたラジオを直していた。必要になれば狩猟に出る。食事時間は特に決まってはおらず、お腹のすいた時に勝手に食べるようだった。
日本と違い、ここでは何かに追い立てられることがない。そのせいか、ゆっくり時が流れているように感じた。
母親のチメグさんを手伝い、モンゴル風肉まんを作ることになった。食用にした牛や羊は、骨から血の一滴まで上手に使い切り、ゴミは出さない。
定住する民族と違い、必要な時、必要な場所へ居を移す、風のような生き方をしてきた彼らは、生きていくのに必要なものだけを手に入れ、使い切る。無駄のない、ある意味洗練された生活スタイルが確立していた。
「文明には程遠い『食て寝て起きて……』の、昔のままの生活です。でも遊牧民たちは、今の日本人が追い求めているもの、ゆとりや自由、誇り、家族愛や郷土愛、そういったものを贅沢なほど持っているんですよ」
頭上に満天の星
その夜、大川さんは終生、忘れえぬ体験をしたという。
ふと目が覚めて、腕時計を見ると午前2時。小さな天窓から星の光が降り注ぐ。その神秘さに釣られて外へ出ると、頭上には満天の星!!
「日本の田舎で見るような星空とも違って、まるで天球に頭を突っ込んだみたいな感じです。あらゆる星座が、挑みかかるように強い光を放つんです。」
モンゴル高原の空気は乾燥して水蒸気が少ないため、無数の星が瞬きもしない。
「しばらく歩くと、闇にも目が慣れ、薄ぼんやりとした大草原が浮かんできました。動いているのは私だけ。風がやむと一切の音の絶えた『無』の世界。時間さえも止まり、怖いような無限大の空間がありました。すると眼前の草原が、無数の人々が現れては消えていった、壮大な墓場に見えたのです。その時、確かに心に〝風〟を感じました。」
万人共通のもの?生老病死?

大阪駅前のレストランで、彼女のモンゴル体験記を聞いていた私は、結局最初に言っていたすさまじい〝風〟とは何だったのか尋ねてみた。
「うーん、それはあそこに行かないと分からないことかもしれません」
つまり、と彼女は言った。
「あの遊牧生活で、草原から世界を眺めると、今までの価値観が根底から揺らぐのです」
それは高学歴、高収入、会社の時価総額、セレブな生活、そういったもの?
「そう、学歴や地位が草原で何の意味があります?
パソコンも情報も、無くても何も困りません。なのに皆が価値があると信じると、本当に価値があるように思えて、それに人生を振り回される。現代社会といっても、それは一つの幻想の上に踊らされているように見えるんです」
確かに遊牧民と比べたら、現代人は無用のものばかり欲しがっているのかもしれない。
そういうことを理屈として理解している人はいると思うけど、体感したのなら、それはすごい、と言うと、
「だから〝すさまじい風〟と言ったんです」。
大川さんは、誤解がないように、と言って付け足した。
「別に私はモンゴル人の生き方がいいと言っているわけではありませんよ。ただ、現代文明というのも、人間の生み出した一つの虚構にすぎないと言いたいんです」
だからそんな社会の中に普遍的な人生の目的を求めても見つかるわけがない、と彼女は言った。草原は人を哲学者にするのかもしれない。
「以前、仏教も一つの考えだ、マインドコントロールだとか言われて動揺したこともありました。でも今は違うんです。そんなことを言っている人自身、仏教がどんなものであるか、よく分かっていないんじゃないでしょうか。自分の信じている価値が本当に確かなのか、誰かの言っていることを鵜呑みにしているだけではないのか、まずそこに批判の目を向けてほしいと思うんです」
そのとおりだと思う、と答えると、彼女は少し言葉を強めて言った。

「大草原の遊牧民であろうと、高層ビルの並ぶ文明社会で暮らす人々であろうと、全く変わらないのが、仏教に説かれる後生の一大事です。蓮如上人の『白骨の御文章』を読んで、モンゴル人には当てはまらない、というような個所は一つもないのですから」
「それ、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに、凡そはかなきものは、この世の始中終、幻の如くなる一期なり」
「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり』──。生老病死の人間の真実を教えた金言ばかりなのに、改めて胸打たれる。
「大草原の〝風〟を聞き、人生の目的が万人共通で唯一といわれる意味が、よく分かった気がするんです」
レストランを出ると、大阪の街には夕闇が迫っていた。
「モンゴルからは日本がどう見えましたか?」
と聞くと、「じゃあ今、高い所から見てみましょうよ」と駅前の高層ビル「HEP FIVE」の屋上の大観覧車に乗ることになった。
頂点から見下ろすと、赤や緑、色鮮やかに瞬くネオンが果てしなく広がっている。
「わあ、モンゴルと反対。まるで地上の星ですね」。
彼女は笑った。
「親鸞聖人の教えを聞き、人生の目的を知る人が増えてほしいですね。」
そう語り合い、観覧車を後にした。
※ モンゴル国……広さは日本の約四倍で、その大半
を大草原とゴビ砂漠が占める。人口は約二百六十万。
大阪市の人口とほぼ同じ。