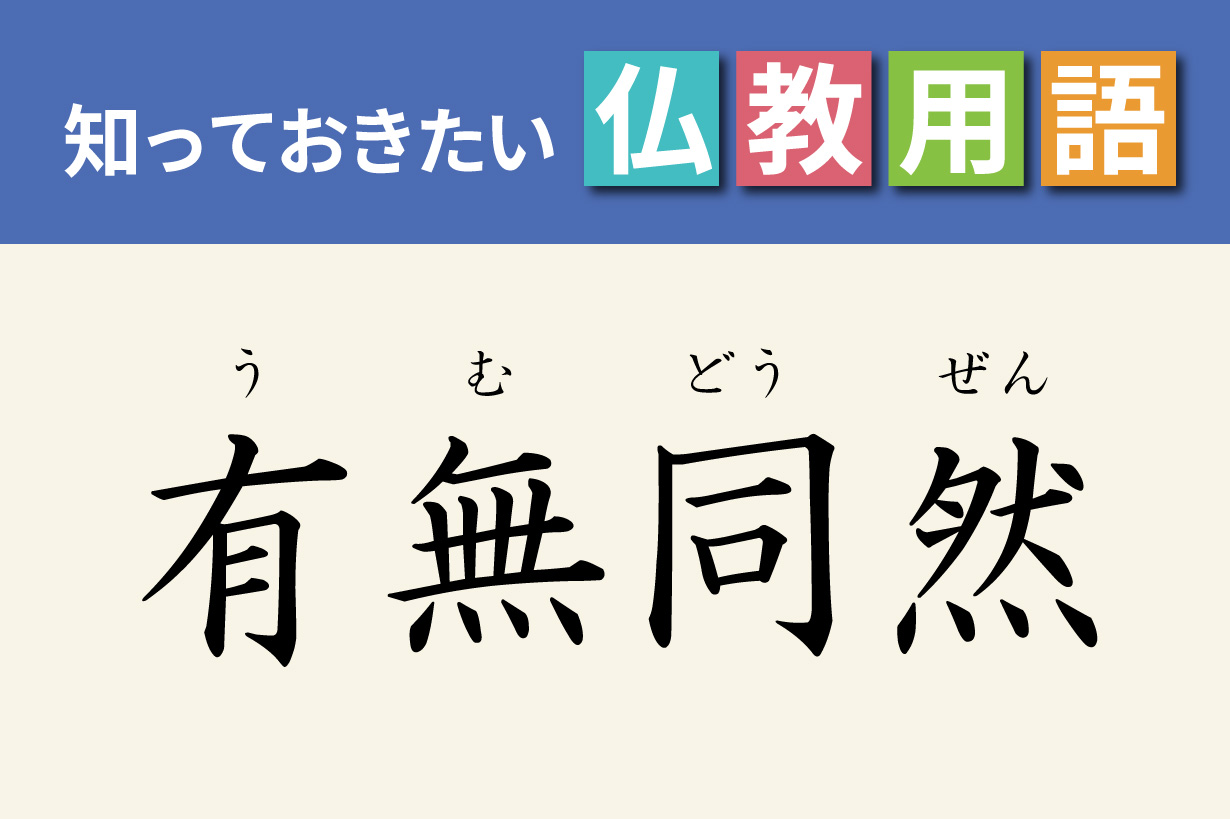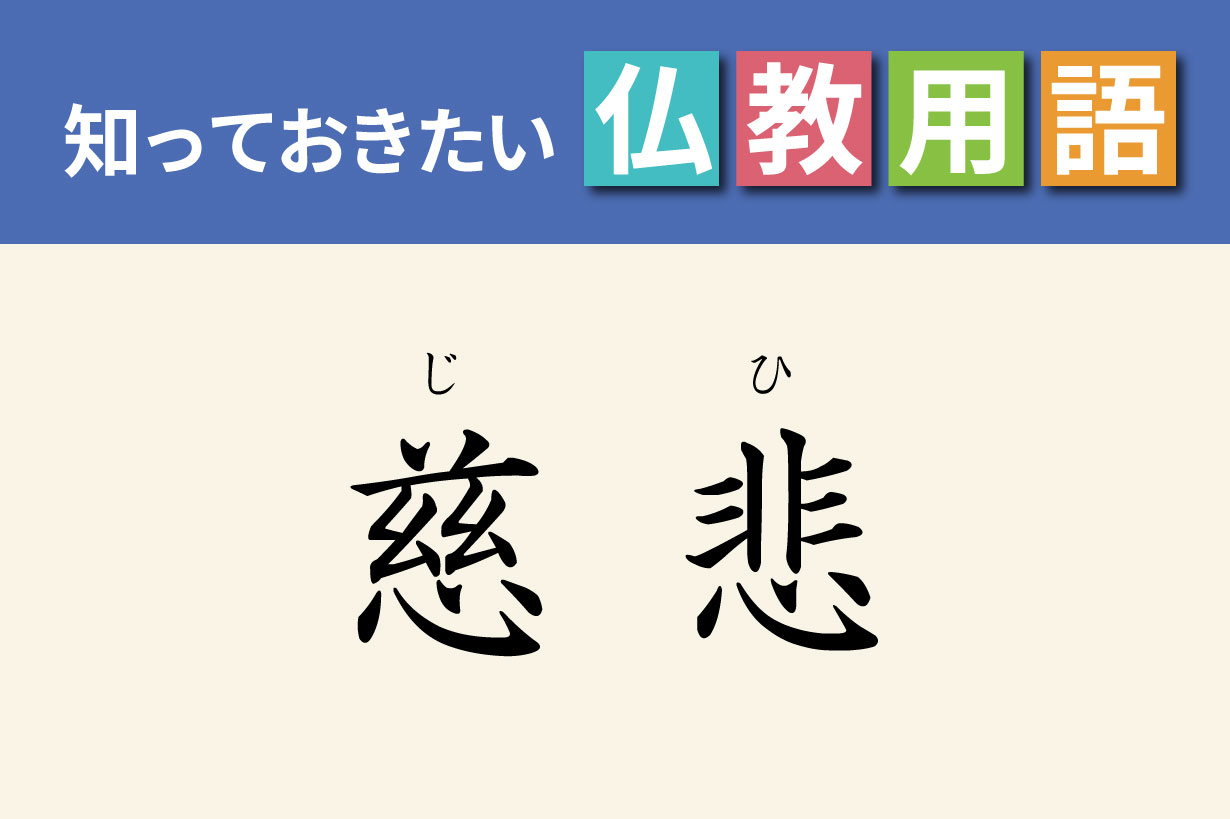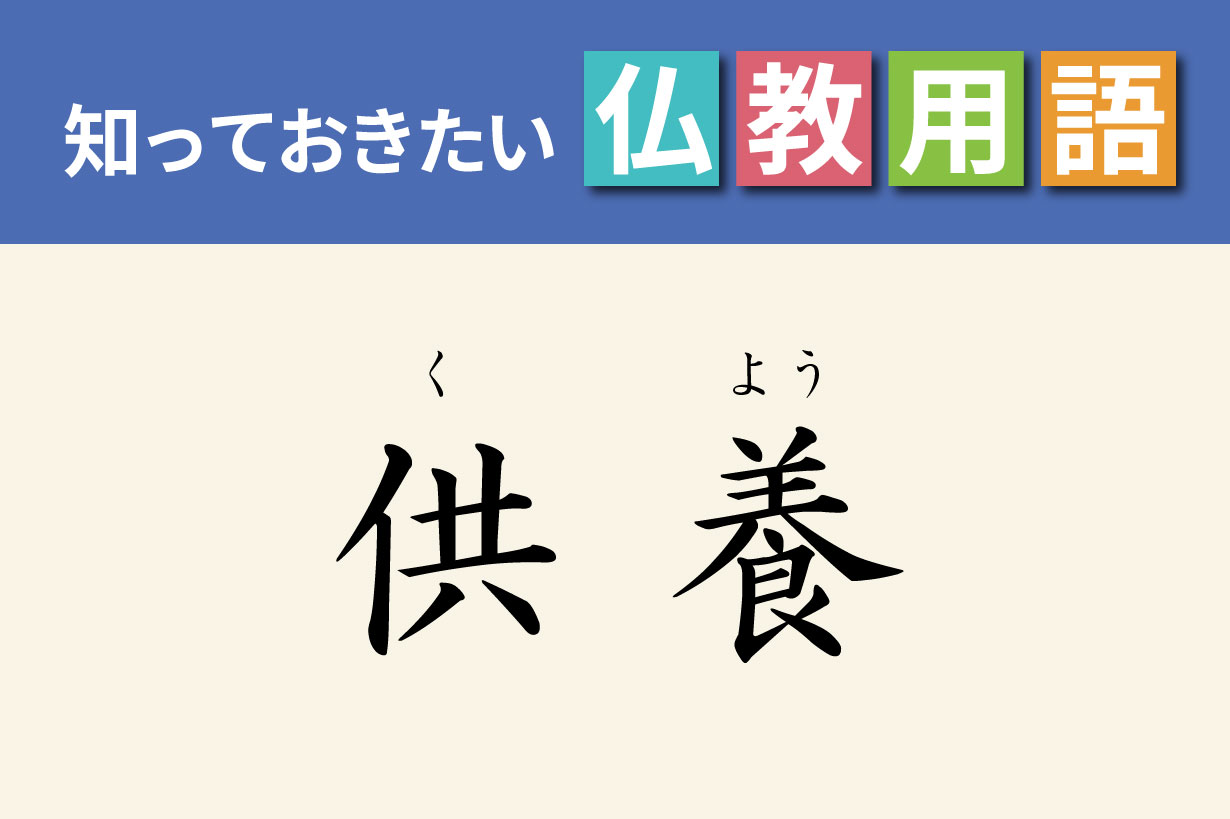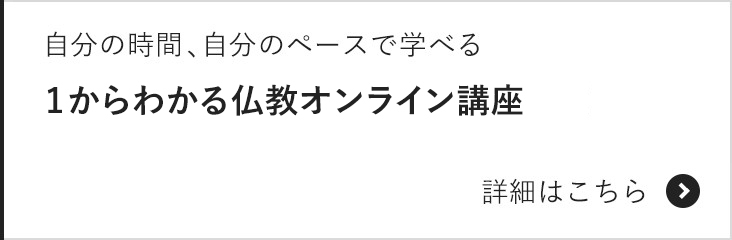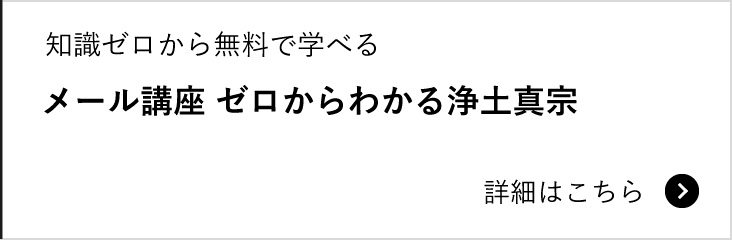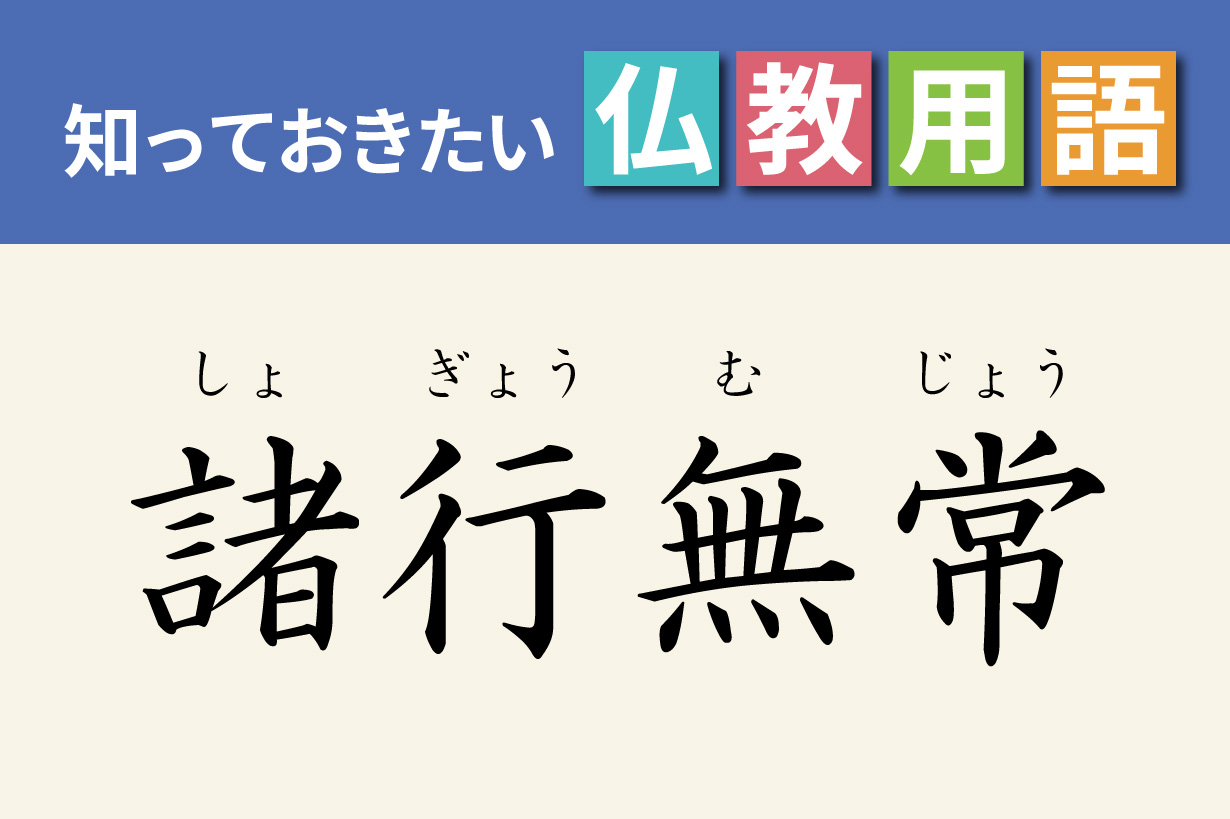
お経とは 分かりやすくて詳しく分かる仏教用語集(動画つき)
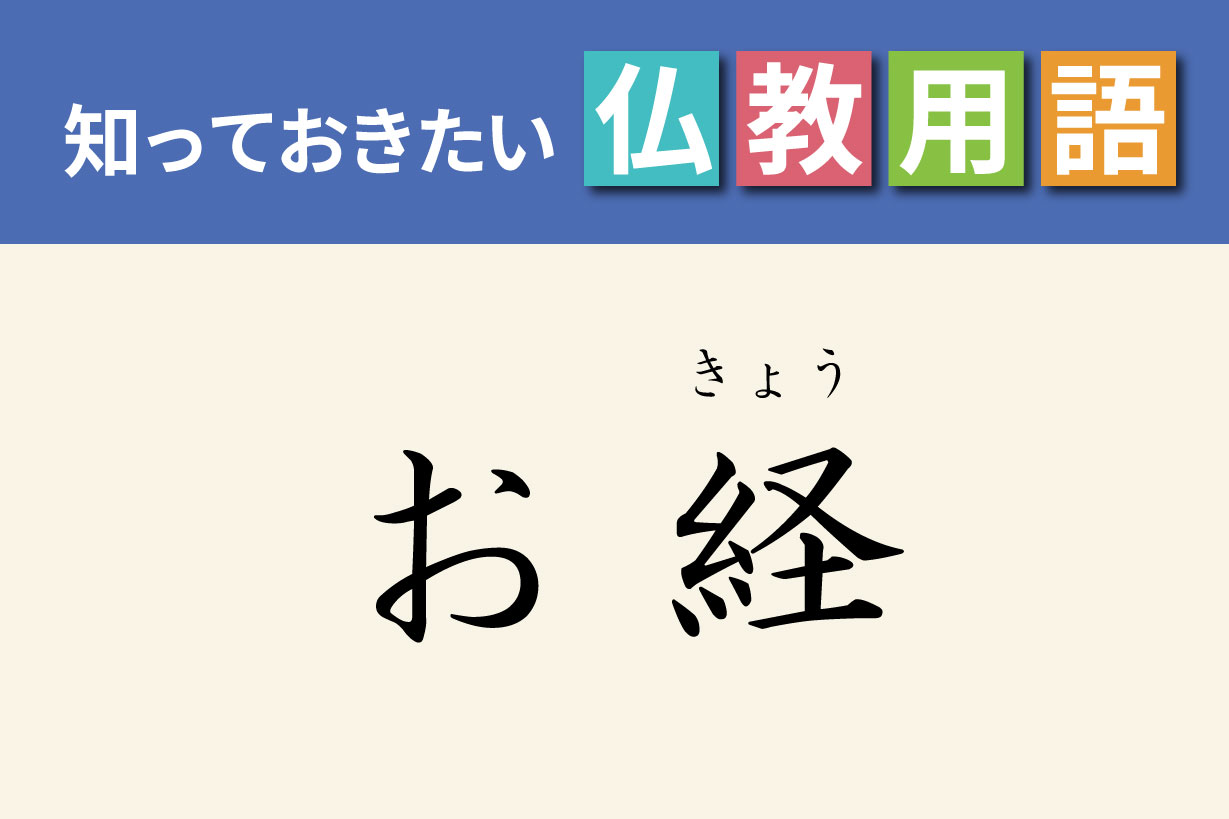
「お経(経典)を読んでもらうだけが死人のごちそうだ」「何よりの供養になる」などという人があります。しかし親鸞聖人は一度も、そのようなことを教えられてはいないのです。そもそもお経とは何なのでしょう。
「お経」と聞いて、まず思い出すのは、葬儀で読まれる場面でしょう。「立派な葬式で、お経を読んでもらったら、亡くなった人の供養になる」と思っている方も多いと思います。ただ、実は「お経」とは、亡くなった人のために存在するというよりも、むしろ、逆なんです。「お経」というものが、どのようにしてできたのか、その成り立ちの因縁を知れば、逆だという理由を、あっさり、知ることができますよ。
『西遊記』にも出てくる「お経」の正体は?
「お経」は、「経典」とか「仏典」ともいわれます。約2600年前、インドで仏教を説かれた釈迦の言葉が記録されているものです。釈迦とは、手塚治虫の長編マンガ『ブッダ』の主人公、お釈迦様のことです。「ブッダ」とは、漢字では「仏陀」と書きます。「仏のさとり」を開かれた方という意味です。
お釈迦様は、生まれた時から「ブッダ」では、ありませんでした。「ブッダ」となられたのは、35歳12月8日のことです。それから、80歳2月15日に、お亡くなりになるまでの45年間、仏としてさとられた真理を伝えられました。その45年間、釈迦が説いた教えを、今日「仏教」といわれるのです。
2600年も前に説かれた仏教を、現代の私たちは、どうして知ることができるのかといえば、その45年間の釈迦の説法が全て記録されているからです。その言わば“講演記録”が、「お経」なのです。
伝奇小説『西遊記』などで、インドから中国へ、多くの経典が運ばれるエピソードは、よく知られていますね。なにしろ、45年間の説法ですから「お経」の数は膨大となり、全部で7000冊以上になっています。当時は「巻き物」でしたので「七千余巻」といわれます。それら全てのお経を総称して「一切経」とも呼ばれます。
お経が「如是我聞」で始まる理由
では、そもそも、「お経」は、どのようにして成立したのでしょう。
お釈迦様が、亡くなられたあと、優れた500人の弟子が集まり、釈迦の説法の内容をまとめました。これを「仏典結集」といいます。この時、中心的役割を果たしたのが、阿難というお弟子です。阿難は、お釈迦様に長く随行し、ご説法を最も多く聴聞していたことから「多聞第一」のお弟子といわれます。記憶力抜群で、お聞きしたことを非常によく覚えていたのです。
その阿難がまず、「私はこのようにお釈迦様からお聞きしました」と語り、他の多くの仏弟子たちが、その内容に間違いがないかを徹底討議し、全員一致した内容だけを書記が記録したと伝えられます。どの経典も、「如是我聞(にょぜがもん・是の如く、我聞く)」とか「我聞如是(がもんにょぜ)」と始まっているのは、そのためです。
ですから、7000冊以上のお経の中身は、全て、“生きている人”を相手に、お釈迦様が説かれたものばかりで、“亡くなった人”を相手に説かれたものはなかったということです。
葬儀での読経は無意味なの?
では、葬儀や法事で「お経」が読まれることは無意味なのか?というと、そうではありません。本来の葬儀や法事とは、読経のあとに、お経に書かれている釈迦の教えを、参列した人たちが聞かせていただくご縁だからです。
どんな人の一生も、必ず終わりを迎える時があります。生まれたからには、どうあっても、死んでいかねばなりません。これだけは、AI時代になっても、代わってもらうことはできません。
「お経」には、“必ず死ぬのに、なぜ、苦しくとも生きねばならないのか”という問題の答え、人生の目的が明かされています。亡くなられた方を縁として、葬儀や法事で「お経」に書かれた釈迦の言葉を聞くことは、限りある人生を見つめ、その目的を考えるきっかけになるでしょう。
【まとめ】お経とは
- 「お経」の正体は釈迦の講演録
- 「お経」は「仏典結集」で成立
- 「お経」が葬儀で読まれる本来の意味